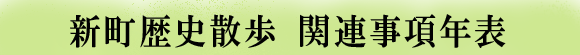|
[目次][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][18別編][19][20][21][22][23][24][25][年表]
山田治信氏の新町歴史散歩 附録
平成25(2013)年3月
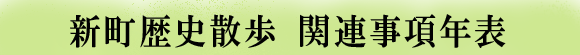
新町歴史散歩年表
| 西暦 | 年号 | 年 | 内容・事項 | 掲載No. |
| (平安時代) |
| 807 | 大同 | 2 | 生野銀山開坑説 | 11,16 |
| (室町・戦国) |
| 1542 | 天文 | 11 | 生野銀山の中興 | 2,16 |
| 銀山旧記はこの頃からの記述で始まる |
山名祐豊、生野銀山を所領と宣言統治に入る
観音像を入手、一堂を建立(仙遊寺の前身) |
| 1553 | 〃 | 22 | 奥山神建立(口山神建立 永元元年(1521)) | 16 |
| 1556 | 弘治 | 2 | 竹田城主太田垣朝廷、謀叛し生野を所領 | 2 |
| 1567 | 永禄 | 10 | 金香瀬大谷筋奥堀切りに山出来て銀出る | 11 |
| 1570 | 元亀 | 元 | 小野所属の山々が発見採掘に入る | 11 |
| 1577 | 天正 | 5 | 豊臣の軍勢但馬に進攻
生野銀山も織田・豊臣の時代に入る | 2 |
| (安土・桃山) |
| 1578 | 天正 | 6 | 信長が代官を派遣、奉行所の始まり | 11 |
| 1582 | 〃 | 10 | 羽柴秀吉代官を派遣 | 11 |
| 1585 | 〃 | 13 | 初めて小野大橋が架かる(日本歴史地名大系) | 11 |
| 1587 | 〃 | 15 | 山神祭の始まり | 19 |
| 1593 | 文禄 | 2 | 一誉和尚仙遊寺再興 | 2 |
| 1600 | 慶長 | 5 | 間宮新左衛門 徳川の初代代官に付く | 11 |
| 奥銀谷、新町など谷に人家増え次第に繁盛 | 7 |
| 白口は880軒を数える | 11 |
| (江戸前期) |
| 1614 | 慶長 | 19 | 大坂冬の陣、間宮代官 奥地区代表・坑夫参陣 | 5 |
| 1660 | 万治 | 3 | 石が出ず山がさびれて人は他の山に去る | 11 |
| 奥銀谷大火、加奉の苗字・帯刀許可状焼失 | 5 |
| 1665 | 寛文 | 5 | 竹原野 道雲山に鉉出てやや持ち直す | 11 |
| 1668 | 〃 | 8 | つづら畑(久宝ダム下)新町久太夫山に鉉出る | 11 |
| 1680 | 延宝 | 8 | 白口蟹谷重良兵ヱ、山神に祈り良い鉱脈が出る | 11,16 |
| 1682 | 天和 | 2 | 上山重良兵ヱ、神輿再興・蟹の像を造る | 11,16 |
| 1683 | 〃 | 3 | 銀山廻り茶改め帳に鋳師(いもじ)町の名 | 7 |
| 銀山旧記の記述の終わり頃 | 23 |
| (江戸中期) |
| 1692 | 元禄 | 5 | 大用寺衆寮(現大用寺の元の建物)建つ | 21 |
| 1704 | 宝永 | 元 | 銀山大火 口銀谷町より竹原野まで焼失 | 5 |
| 1705 | 〃 | 2 | 菊谷勘兵衛、若林山盛り大山師にのし上がる | 7,11 |
| 若林勘兵衛山が初めて見石を出す | 19 |
| 1720 | 享保 | 5 | 奥地区代表 代官所の取扱いに怒り申入れ | 5 |
| 1751 | 宝暦 | | 1751~1764年頃、下箒桟道架かる | 8 |
| 1754 | 〃 | 4 | 新町竹田屋忠太郎、小野油屋関助の経営する
得受・双宣山盛り後に私札双宣札を発行 | 11 |
| 1764 | 明和 | 元 | 新町川向、緑青山(緑珠)御所務山となる | 11 |
| 1767 | 〃 | 4 | 下箒、築地(ついじ)の道となる | 8 |
| 二本松下(現旧学校)へ神宮寺移る | 6 |
| 若林山出水で採掘中断 | 11 |
| 1769 | 〃 | 6 | 新町大火 | 5, 6,11 |
| 1770 | 〃 | 7 | 大用寺より出火、寺町(奥銀屋)ことごとく焼失 | 21 |
| 新町川向、早谷久林山大盛り | 11 |
| 1771 | 〃 | 8 | 新町大火で焼けた神宮寺再建 | 6 |
| 御所務山始め留め書き | 7 |
| 新町の買吹忠太郎鉑石を堀あて双繋山と名付ける | 11 |
| 1776 | 安永 | 6 | 奥山神に鰐口奉掛(小野井瀬町、九蔵・仙蔵・辰吉 | 7,16 |
| 新町、朝来屋五助が大谷筋登り谷で石銀堀あてる | 11 |
| 1783 | 天明 | 3 | 奥山神漆谷山の峯より二本松下の神宮寺に遷座 | 6 |
| (江戸後期) |
| 1785 | 天明 | 5 | 下箒の道雨で流出、前借り借財で補修 | 8 |
| 1792 | 寛政 | 4 | 生野銀山間歩字附表記される | 22 |
| 1794 | 〃 | 6 | 下箒相対死(心中) | 9 |
| 1796 | 〃 | 8 | 金毘羅社を大用寺に建立寄進 山師 穐山平兵衛 | |
| 1797 | 〃 | 9 | 十六羅漢神宮寺に建立 | 21 |
| 1803 | 享和 | 3 | 二本松の奥山神に稲荷大明神を請い併せ祀る | 6 |
| 1811 | 文化 | 8 | 徳本上人生野に | 4 |
| ? | 〃 | ? | 桐の木稲荷建立(この頃、文化年間) | 20 |
| 1812 | 〃 | 9 | 山神祭に南光院の法螺貝出る | 19 |
| 1817 | 〃 | 14 | 白口本谷庵の名号碑建立 | 4 |
| 1829 | 文政 | 12 | 相沢稲荷霊験記(悲話)にある大丸坑出水 | 20 |
| 1830 | 〃 | 13 | 地役人大塚重蔵芳賢の「大亀祝言」新町漆垣家に | 19 |
| 1833 | 天保 | 4 | 下箒の道を三山師が補修、供養塔を建てる | 8 |
| 1837 | 〃 | 8 | 天受ひ 御所務山となる | 14 |
| 1843 | 〃 | 14 | 天保期の大坂三郷図の町名に奥地区代表の名が残る | 5 |
| 1853 | 嘉永 | 6 | 若林山師太田作兵衛 蟹谷尊像に再興を祈る | 16 |
| 1854 | 〃 | 7 | 本来寺名号碑建立 | 4 |
| 1863 | 文久 | 3 | 三大山師奥山神に戸張3垂 奉納 | 16 |
| お銀飛脚井筒屋と生野の変 | 1 |
| 1867 | 慶応 | 3 | 鉱山最衰期 全山休山状態(鉱業編P51) | |
| 1868 | 〃 | 4 | (明治元年) 官軍生野占拠、神仏分離令 | 7 |
| 鉱山官営となる | 18 |
| (明治) |
| 1869 | 明治 | 2 | 町内の町名が改められた、口銀谷は○丁目制に | 7 |
| 1870 | 〃 | 3 | この頃、毘沙門天 仙遊寺に遷座(神仏分離令) | 2 |
| 1871 | 〃 | 4 | 新町川向までのトロッコ道建設に着手 | 13 |
| 1872 | 〃 | 5 | 猪野々に外人技術者の住宅を建設 | 18 |
| 葛籠畑(つづら畑)田畑開発を始める | 22 |
| 1873 | 〃 | 6 | 桐の木稲荷 村社として修復 | 20 |
| 1874 | 〃 | 7 | 奥銀谷小学校創立(奥銀谷町字蔵屋敷の官有米蔵を校舎として) | 6 |
| 1875 | 〃 | 8 | 別所家文書と つづら畑及び火薬庫 | 24 |
| | 〃 | ? | 引 札 | 17 |
| 1876 | 〃 | 9 | 竹原野鷹の巣ダムおよび水路完成 | 12 |
| 1877 | 〃 | 10 | この頃より新町に官舎・社宅が出来始めたのではないか(これは編者予想) | 18 |
| 1889 | 〃 | 22 | 皇室財産に移管、宮内省御料局の所管となる | 8 |
| 大雨による大洪水、奥銀谷・新町の下町浸水し竹原野より応援、のち竹原野の橋2か所が流失し応援者帰れず | 7 |
| 相沢町大水害で埋没 | 7 |
| 下箒道路流失、再々築し現在の路の基礎を造る(修道碑文の日付は23年8月) | 8 |
| 1891 | 〃 | 24 | 奥山神二本松下より現山神宮付近に遷座 | 2, 6 |
| 1892 | 〃 | 25 | 山神宮新しい場所で最初の山神祭 | 19 |
| 二本松下に奥小学校が漆谷米蔵より移転 | 2, 6 |
| 十六羅漢大用寺に移設 | 21 |
| 相沢町鉱業用地として買収 | 20 |
| 1893 | 〃 | 26 | 馬淵ダム・新水路着工 | 12 |
| 1896 | 〃 | 29 | 生野鉱山三菱へ払下げ | |
| 1901 | 〃 | 34 | 久宝に2番坑開坑 | 22 |
| 1902 | 〃 | 35 | トロッコ道(鉱山軽便軌道敷設道路)電灯点く | 17 |
| 1904 | 〃 | 37 | 奥銀谷小学校二本松下より前(現)学校用地に移転 | 6 |
| 1909 | 〃 | 42 | 久宝2番坑採掘中止 | 22 |
| (大正) |
| 1913 | 大正 | 2 | 金香瀬坑内光栄竪坑付近より出火、40日余休止
川向のトロッコ道延長、下町筋道路のトロッコ道無くなる | 13 |
| 電燈が架設された | 17 |
| 1916 | 〃 | 5 | 部屋主の廃業や鉱夫直轄制度がぼつぼつ始まる | 18 |
| 1917 | 〃 | 6 | 索道が初めて久宝に架かる | 22 |
| 1918 | 〃 | 7 | 乗合自動車が生野駅~小野間を走りだす | 17 |
| 1919 | 〃 | 8 | トロッコ路電化 | 13 |
| 1921 | 〃 | 10 | この頃、西寶寺が一時幼児の預かり所を運営 | 10 |
| 力泉寮(鉱員合宿所)の前身が猪野々に出来る | 22 |
| 1925 | 〃 | 14 | 労働争議大紛争に発展、能見町長・安井県議・町有力者調停に入り、罷業(スト)中止 | 17 |
| (昭和) |
| 1928 | 昭和 | 3 | 鉄筋のつづら橋架かる | 22 |
| 1929 | 〃 | 4 | 久宝にダム建設を決定、5年完成 索道架かる | 22 |
| 1931 | 〃 | 6 | 幼稚園が町立として奥銀谷小学校に併設される | 10,17 |
| 1938 | 〃 | 13 | 緑珠旧採掘跡下に富鉱帯発見 | 14 |
| 請願巡査制度廃止 | 13 |
| 国家総動員法発布 | 18 |
| 1939 | 〃 | 14 | 銀谷寮建設 | 18 |
| 1940 | 〃 | 15 | 国民服令制定 | 10 |
| 1943 | 〃 | 18 | 小学校の部落分けは新町東部・西部となっていた | 10 |
| 軍歌を歌って登校 | 10,20 |
| 1944 | 〃 | 19 | 旧制中学生・女学生白口で炭焼き、薪取り | 4 |
| 中学生隊列を組んで登校 | 10 |
| 1945 | 〃 | 20 | 終戦 朝鮮人の戦勝大行進
連合軍捕虜収容所に落下傘で物資投下 | 18別 |
| 1949 | 〃 | 21 | 新町郵便局開局(八鹿電気新町工場付近 旧幼稚園跡) | 17 |
| 1948 | 〃 | 23 | 生野第一保育所を唯念寺に開設 | 15 |
| 社宅地区が新町・奥銀谷より分離扇山区として独立 | 18 |
| 1954 | 〃 | 29 | 生野町制65周年記念誌発刊される | 17,22 |
| 1955 | 〃 | 30 | 充填採掘法採用 | 14 |
| 1956 | 〃 | 31 | 緑が丘区分離独立 | 18 |
| 1959 | 〃 | 34 | 久宝ダム下の廃泥を覆土 | 22 |
| 1961 | 〃 | 36 | 新町橋が永久橋に変わる | 3,17 |
| 新町郵便局 現在地に移転 | 17 |
| 1964 | 〃 | 39 | 仙遊寺廃寺、跡地に第一保育所を移設 | 2,16 |
| 奥山神・神宮寺仏像本来寺に遷座 | 2 |
| 1965 | 〃 | 40 | 久宝ダムに報道ヘリコププター降りる | 22 |
| 1966 | 〃 | 41 | 上町筋が一方通行となる | 17 |
| 1968 | 〃 | 43 | カドミ公害問題発生 | 12 |
| 1969 | 〃 | 44 | 山神宮考発表(生野町偕和 柏村儀作氏) | 16 |
| 1973 | 〃 | 48 | 生野鉱山閉山 | |
| 1977 | 〃 | 52 | 新町公民館建設 | 17 |
| 1988 | 〃 | 63 | 新町郵便局局舎新築 | 17 |
| (平成) |
| 1989 | 平成 | 元 | 町制100周年〔明治22(1889)年市町村制施行〕 | |
| 1997 | 〃 | 9 | 立松和平氏「恩寵の谷」発表 | 21 |
| 1999 | 〃 | 11 | 新町ふれあいセンター開所(9月15日) | 1 |
| 2005 | 〃 | 17 | 町村合併朝来市へ | |
| 2008 | 〃 | 20 | 「新町毘沙門天詞堂の中の歴史」発刊 | 16 |
| 2009 | 〃 | 21 | 「旧坑・間歩の字附表=山田・椿野氏纂」発刊 | 各 |
| 奥銀谷小学校閉校 | 10 |
| 水路より溝への給水止まる | 12 |
| 2010 | 〃 | 22 | 漆谷庵の観音像大用寺に併せ祀られる | 21 |
| 「うちやまさん物語」佐藤文夫著 発行 | 7 |
| 2011 | 〃 | 23 | (廃)仙遊寺に加奉建立の墓を発見 | 25 |

このページは、ワード文書としてA4用紙5ページにまとめられた「新町歴史散歩 関連事項年表」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami)

|