


|
||||||
| 【最終更新日:2011/5/21】 | ||||||
|
[目次][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][18別編][19][20][21][22][23][24][25][年表] 山田治信氏の新町歴史散歩 3平成23(2011)年5月 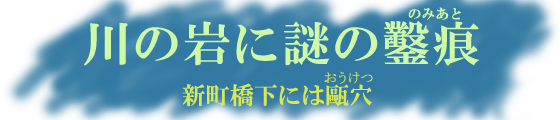
新町下町の川の対岸にある崖下の細い道は、鉱山がある頃、金香瀬(採鉱=鉱石を掘る現場)に資材を運んだ電車の道でした。
しかし柏村氏は、ここで面白いお話をつけ加えておられます。万治3(1660)年頃、生野の諸山は衰退して多くの稼人は他所の山へ移り、火の消えたような状態となりました。無知な稼人たちは、これは魑魅魍魎(ちみもうりょう=山・川・木・石より異気を発する怪物)の仕業に違いないと恐れ、長刀を彫らせて退散を祈ったのではないか。また一つに、白口諸山で採掘した銀石を製錬するため、新町、奥銀谷の吹屋に運ぶための道筋に安全を祈って彫ったのではないか。新町で川の中に彫ってあるのは、当時の道が猪野々から川に降りて川筋を渡り、新町に上がったのではないかというものです。
しかし石が回転して穴を掘るなど現在の水量や流れの速さでは考えられませんが、昔下箒の断崖の下は深い淵になっており、激流が何度となく断崖を襲ったということで、ここに道路を造るためには幾多の困難な歴史があったようですから、当時の地形や激流を想像してみるしかありません。
(文・構成 山田治信) ( こぼれ話 新 町 橋 ) 新町橋は、猪野々から金香瀬に通勤するために大勢の人が利用した重要な通路でした。木の橋の上の路面は石混じりの土で蒲鉾のように真中が盛り上がっており、木の欄干は低くて自転車などでは、真中を通らないともし横に倒れたら川へ落ちそうな感じで怖かったです。 (文 編 者) 
このページは、ワード文書としてA4用紙3ページにまとめられた「新町歴史散歩No.3」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami) |
Copyright(C) 2009 奥銀谷地域自治協議会 All Rights Reserved. 禁無断転載 Design by K-TECH Co.,Ltd.


